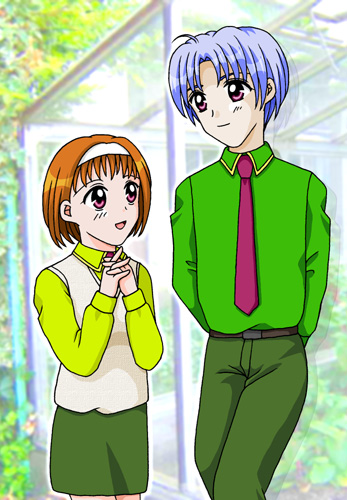
それから3ヶ月の時が過ぎた。
雪彦と恵莉が付き合っている、という噂は瞬く間に広まり、
気が付くと二人は既に公認のカップルになっていた。
部署も違い、普段いるフロアも全く違う二人は、
昼休みは屋上公園で一緒にお弁当を食べ、
帰りはお互い残業がなければデート、という日々を繰り返していた。
だが、楽しい日々の陰で、恵莉は足繁く図書館や古書店などに通い、
雪女伝説について熱心に調べていた。
長生きできる方法を探す、と彼に宣言したが、彼の心を傷つけないように
会話ではなるべく、その事には触れないようにしていた。
そして雪彦も……彼女との日々がとても楽しいと思う中で、
心の奥ではやはり寿命のこと、この先のことが重く引っかかっていた。
「『それじゃ、おやすみ』……と。」
恵莉におやすみのメールを送った後、雪彦は自室のベッドに横たわり、一息ついた。
(……5年……5年あるかどうか、わからないけど……)
『残り5年だと言うなら、なぜその5年で幸せにしてやろうと思えない?
5年の努力が出来ない奴には、100年生きたって何も出来やしないよ』
雪彦の心の中では、あの時夜半に言われた言葉がずっと突き刺さっていた。
どうすれば5年で、彼女を幸せにすることができるんだろう?一体何をすればいいんだろう?
自分が死んだあとに、彼女に、自分の恋人で良かったと思わせるには、どうすればいいのだろう?
恵莉は、何も言わないが、密かに雪女族について色々と調べ、
どうにか寿命を延ばす方法がないかと調べているのは、薄々気づいていた。
だがそんな方法があるとするならば、雪女族である自分も知っているだろうし、とっくに試している。
(母さんや……姉さんに訊いたら、わかるのかなぁ……)
雪彦の東北の実家には母と姉がいるが、二人とも男は短命であることは重々承知で、
彼があと数年で死ぬことも、恐らく仕方のないことだと割り切っている。
”ピンポーン ”
ベッドの上で悶々としていると、夜中の0時を回っているにもかかわらず、ドアチャイムが鳴った。
こんな時間に訪ねてくる者とは……。
来訪者をある程度予測しつつ、雪彦は玄関モニターを覗き込んだ。
「久しぶりね雪彦。…さすがにもうすぐ8月だし、夜でも結構暑いわね。」
真夜中の来訪者の正体は、雪彦の姉・吹雪(ふぶき)であった。
真っ白い肌に、白に近いブルーの長い髪。
そして、妖しい視線で一瞬にして男を虜にしてしまいそうな美貌の持ち主である。
母にはもう何年も会っていないが、姉は時々都会が恋しくなるようで、
こうして連絡もなしに突然に現れるのは、珍しいことではなかった。
「そうだね……あ、お茶飲む?」
そう言って、雪彦はキッチンへと足を運んだ。
吹雪の視界から雪彦が消えると同時に、ベッドの上に置いてある雪彦の携帯が鳴った。
携帯に視線を向けると、携帯のサブウィンドウに表示された「E-mail受信」という文字と、送信者名が見えた。
(長谷川……恵莉?)
「はい、お茶」
ほどなくして雪彦が戻ってくる。
「ありがと……ねぇ雪彦。もしかして彼女でも出来たの?」
姉の突然の発言に、冷たい緑茶が入ったグラスを落としかける雪彦。
「な……なんで」
「だって今鳴った携帯に女の名前が出てたから。」
「…………」
特に否定する必要もないが、あっさりと見抜かれたことが複雑で、雪彦は気まずそうな顔をした。
「…彼女は、あんたがもう長くないこと、知ってるの?」
気を遣うわけでもなく、当たり前のことのように吹雪が問う。
「…………知ってるよ」
「ふぅん」
大したもんだわ、という顔で緑茶に口を付ける吹雪。
「……ねぇ、姉さん。今まで当たり前だと思って、改めて訊いたことなかったけど…
……男が……僕が、若くして死なずに済む方法って、ないの?」
吹雪は、緑茶を飲む手を止め、しばらく考えた後に答えた。
「あるにはあるわよ」
・
・
・
「……まさん、烏丸さん!」
午後の休憩時間、屋上公園の木陰のベンチ。
隣で何度も呼ぶ恵莉の声に、雪彦はハッとした。
「……だいじょうぶですか?さいきん暑くなってきましたよね。
きょうはわりとすずしいほうですけど……」
昨晩、姉に言われた言葉が頭から離れず、どうしてもボーッとしてしまう。
「なにか……あったんですか?」
どう見ても様子がおかしい雪彦を心配して、恵莉が顔を覗き込む。
彼女に悟られてはいけない。
とっさにそう思った雪彦は、作り笑いをしながら話を逸らす。
「な…なんでもないよ!昨晩うちに姉さんが来てね。
久しぶりだったから夜遅くまで話込んじゃって…ちょっと寝不足なだけ。
君のことも色々訊かれちゃったし…つい、長話に…。」
心配そうだった恵莉の顔が一気に赤くなる。
「な、ながばなしって……お姉さんにわたしのなにをはなしたんですか!?」
何か恥ずかしいことをバラされてはいないかと、雪彦に詰め寄った。
「い…いやぁ、特に変なことは話してないよ……
それより恵莉ちゃん、そろそろ会議の時間でしょ?早く行かないと遠山部長に怒鳴られるよ。」
「! …きゃぁ、もうこんなじかん!?
…烏丸さん、あとでお姉さんになにはなしたかおしえてくださいね!」
恵莉が走り去った後、誰もいない屋上公園。
夏の太陽が木々を照らし、鮮やかな緑色の葉をさらに映えさせている。
今日は7月下旬にしてはさほど暑くはなく、木陰にいれば心地よい陽気だ。
しかし、そんな心地よい空間にいる中で…雪彦の心の中は、重苦しい感情でいっぱいになっていた。
姉から聞かされた、雪女族の男が延命する方法……
(あるんだ……あるんだよ、恵莉ちゃん……
………でも………!!)
考えただけで、吐き気がしてしまう。
気分が悪くなってきた雪彦は、屋上公園を後にして社屋の中に戻ろうとする。
(………まずい、ほんとに、吐きそう……?)
ふらつきながら、なんとか屋上入口の階段まで歩くが……
視界がだんだん暗くなり、息が詰まり、胸が苦しくなる。
(……え……なに……う………)
雪彦はその場に倒れ込み、意識を失った。

・
・
・
(さて、何処に行こう。)
勤務時間中にもかかわらず、仕事を放って社内をブラブラしているのは、夜半。
いつものように自分の席で寝ていたのだが、国際部の冷房が効きすぎてだるくなったため、
もう少し心地の良い、安息の地を求めて席を立ったのだった。
行き先も決まらず適当にうろうろしていると…
(……? 何だこの異様な妖気は)
夜半は、恐らく普通の人間には感じ取れない異常を感じ取る。
その『異常』の元を探るべく、その場を数歩うろうろと歩く。
(上……屋上……?)
ここから屋上への階段は近い。夜半は屋上へと向かった。
屋上への階段に近づくにつれて、夏とは思えない冷気が吹き込んでくる。
国際部の冷房よりしんどいなこれは、と顔をしかめながら階段を上っていく。
すると…屋上の少し手前の踊り場から上が……全て真っ白に凍っている。
そして氷の階段の頂上…屋上の入口に、雪彦が倒れていた。
「烏丸君!」
夜半が呼びかけて、軽く身体を揺すってみても、雪彦は荒く呼吸はしているものの、意識は失ったまま。
(困ったな……病院に連れて行ったところで、何とかなる者ではないだろうからな……)
とりあえず、屋上ではどうしようもない。
どこかに連れて行って寝かせるか、と思った夜半は、雪彦の腕を持ち上げ、抱きかかえようとした。
すると……
持ち上げた腕が、ドロ細工の人形のように千切れてしまった。
(……溶けてる……?)
・
・
・
「……ん……」
雪彦は、ゆっくりと目を開けた。
いつもと違う天井。見慣れない窓、外は真っ暗。
「…………?」
状況をつかむため、ひとつひとつ、記憶を取り戻す。
確か……屋上で恵莉と話していて……その後一人になって……何か気分が悪くなって……
その後は……?
「……夢……?」
「やっと目が覚めたか。」
声の主の方へ顔を向けると、そこには少し疲れた様子の夜半がいた。
「…しらとり…さん…?」
「君は屋上で倒れていて、起こそうにも気が付かないし、かといって救急車呼ぶわけにもいかないし
とりあえず俺の自宅に来てもらった。現在7月28日午後11時。理解した?」
雪彦が知りたいことを簡潔かつ明確に説明する。
まだ意識がもうろうとしているのか、雪彦は微かにうなずくのが精一杯であった。
「…氷漬けの階段と、一面雪景色になっていた屋上を元に戻して、
固まりきってないプリンみたいな君の身体をここまで運ぶのに、久々に魔導なんて使ったからちょっと疲れたよ。
後で久我ちゃんに頼んで輸血用の血でも貰わないとしんどいな。」
夜のせいか口数多めにぼやく夜半だが、今の雪彦にはほとんど聞こえなかった。
「…白鳥さん…」
「ん?」
「ぼく……わかんないですよ……どうしたらいいんですか……
ぼくはこんなに好きなのに…彼女のこと好きなのに……
近づけば近づくほど、傷つけてしまいそうで……こわくて……
どうすれば…あと何年かしかないのに…しあわせにしてあげられるんですか……
死なずに済む方法…あったけど……あんなの無理だし……
……もぉ……わかんないですよぉ……」
まるで駄々をこねる子供のように、心の内を吐き出す。
どうすれば彼女を幸せに出来るのか。
答えは、夜半でなくとも、誰も知らない。
雪彦の問いの答えを唯一持つのは、恵莉だけである。
それは、雪彦もわかっていることなのだが……
目を虚ろにしてぐずる雪彦の額に、夜半がそっと手を乗せる。
「とりあえず、今は喋るな。興奮して熱が上がるだろう。
今夜はこのまま寝ていいよ、治ったら色々聞いてやるから。」
夏にもかかわらず、少しひんやりとした夜半の手に、
雪彦は心地よさを覚え、「すいません」と小声で呟いた後、再び眠りに落ちていった。
夜泣きをする子供を落ち着かせたあとのように、夜半は深いため息をつくと
さきほど雪彦が、うわごとで吐露した言葉を思い出した。
「何か、死なずに済む方法があったのか…?」

